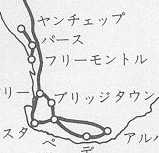
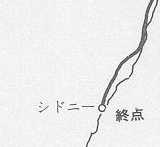



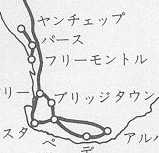 |
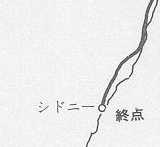 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
① イソメがいそうな波打ち際の砂浜上で、糸に魚のアラをつけて、波が引き終わる頃左右にふる。 ② イソメが匂いやエサにつられて頭を1~2ミリだす。 ③ イソメの居場所がわかったら、イソメに別の上等な魚肉片を食いつかせる。 ④ 片足をそっとだして、足指の間でイソメを挟める体勢をつくる。 ⑤ エサを少し持ち上げて、夢中で食いついているイソメの頭を3~5ミリ持ち上げる。 ⑥ タイミングを見計らって、足の指間で挟み、足を上げて砂の中から引きぬく。私は、足指では100%不可能だから、手指や毛抜きを使ってみたが、頭がちぎれたりした、わずかしかとれなかった。このエサの食いが良いのはここでも同じである。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |