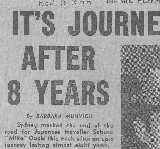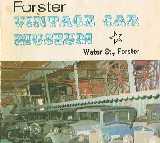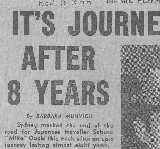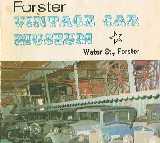海外では、多くのことを考えさせられたが、その一つは日本人とは何か、である。この場ではプラ
ス・マイナス面を1ずつ指摘し、みなさんの感想を求めたい。
① 少しずつ崩れてきたとはいえ、村文化を継承し善意・信頼を基本として社会を運営している民族。
② 国際社会における国の経済規模や政治的影響が非常に大きくなったのに、一方では国の運営を
した経験があまりに少なく、これらについては、相変わらず「見ざる・聞かざる・言わざる」
の封建時代そのままのメンタリティーで対応している民族。
ぜひ、みなさんには、日本の過去と現在を比較して分析してほしい。
「変わった点は何か」、「それのプラス面は何か、マイナス面は何か、そして、どちらともいえない
面は何か」。
「変わらない点は何か」、「それのプラス面は何か、マイナス面は何か、そして、どちらともいえな
い面は何か」。
そして、これらの分析で何が大切かを考え、もしそれらに対して対策が必要なら、その対応策の策
定、実施時期、実施方法等について、自分の意見をもってほしいと思う。なぜなら、これらが自分の
生活に直結しており、これらのなりゆきから逃げられない運命にあるからである。実際、世界には、
これらのなりゆきの帰結が、インフレになって長年の苦労が水泡に帰したり、避難民になったり、豊
かな人生を謳歌させたりするのである。