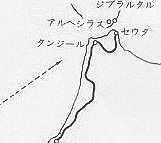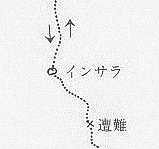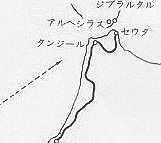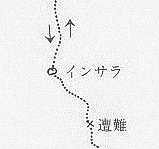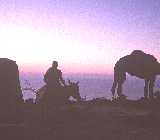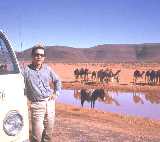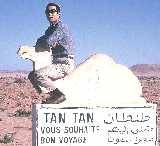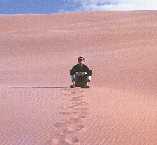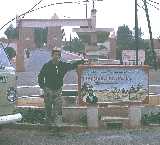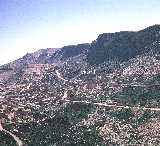1)砂漠には何もないところが多いから、全体的な方向を磁石で確かめながら、ワダチの方向を決め
る。地平線に丘陵等があれば、方向性の参考にする。夜は危険すぎる。
2)ワダチは四方八方に走っているので、自分の目的方向から大きく外れないように注意する。さも
ないと、どこにゆくのかわからず危険である。
3)なるべく新鮮で、多くの車が走った後のワダチを探して走る。ワダチが細くて古いと危険である。
4)タイヤの空気圧を1〜2割下げ、砂との設置面積を大くして、キックする力をつける。空気圧が
正常だと、ただ砂を蹴散らすだけで、埋まりやすい。
5)ソフトサンドを渡るときは、なるべくハンドルを切らない。ハンドルを切ると埋まりやすい。
6)ソフトサンドは、時速40〜60kmで勢いをつけて渡る。ゆっくり渡ると、車が砂に埋まりや
すい。セカンドかサードギアーで、突っ走る。巾が10m以上は猛然と突っ込み、勢いで渡りき
る。トップギアーではタイヤがソフトサンドにとられ、止まりそうになったとき、タイヤを回転
させることができないで埋まる。
7)ソフトサンドには、ときどき他の車が埋まって、砂を除去して脱出したときにつくった大穴があ
る。速度をつけすぎると、この穴の発見が遅れて突っ込み、大きくバウンドして車を傷め、砂に
埋まりやすい。回避しようと急ブレーキを踏むと、車内の荷物がすべて前方に吹っ飛んでくる。
(バケツに野菜の浅漬けをつくっておいたら、車内にぶちまけられた)大穴を回避するために急
ハンドルを切ると、転倒しやすい。したがって、適度の速度をだしながら走り、事前にこの穴を
発見して、なるべくさける。間に合わず、やむを得ず突っ込むときは、なるべくハンドルは切ら
ず、勢いで渡る。ソフトサンドの巾が広ければ、そのままの勢いで渡る。なるべく衝撃を和らげ
るため、多少ブレーキを踏んでも勢いで渡れそうなら、ブレーキ操作をする。
これらを繰り返しても、砂地の状況によっては、たびたび砂に埋まるので、その脱出法。
1)車体の下の、前後輪の前方の砂を、シャベルや手でかきだす。
2)ジャッキで後輪を浮かす。ハシゴ等を敷く箇所以外の位置に、ジャッキ沈下防止用の板等を敷き、
これにジャッキを載せて車を上げる。
3)ハシゴ等の後部端を後輪の下に敷き、ハシゴ等の前部の端は、前輪後部に置く。ハシゴ等の長さ
は、前輪後部から後輪の下までとする。後は、ハシゴ等が動かないように少し砂をかける。
4)ハンドルは真直ぐ保ち、ゆっくり前進する。また砂に埋まる前に止まり、これを繰り返す。ハン
ドルを切ると、また埋まりやすい。
×もし、前輪の前方にも敷き、ハシゴ等を計4個敷くと、車が前進した後、前のハシゴ等が前輪と
後輪の間に入ったときは、砂やタイヤに蹴られて定位置が定まらず、車の底部に挟まって車を傷
めるので、採用できない。また、ハシゴ等を長くして2本にすると、後輪から前輪前方数mの長
さでは、砂の除去をすべて均等の深さにしなければならず、無駄が多すぎて実用的ではない。こ
のハシゴ等は泥道にも使うので、ハシゴ等の長さは3)の長さがよい。
1回の脱出作業でも、心中は不安になる。のどが渇く。手に傷ができやすい。落ち着いて行うこと。これらの理由から、車は頑丈で重量は極力軽くし、効きが悪いショックアブソーバーは新品と交換して万全にしておくこと。