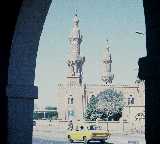




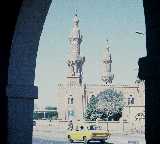 |
 |
 |
 |
 |
 |
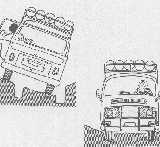 |
 |
 |
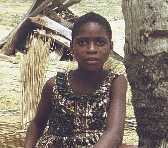 |
 |
 |
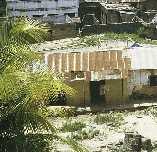 |
 |
 |
 |
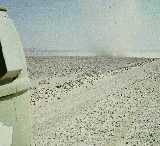 |
 |
 |
 |
丂嘆丂僄僕僾僩偐傜僗乕僟儞僿 丂嘇丂傾儖僕僃儕傾偺僞儅儞儔僙僢僩偐傜僯僕僃乕儖偺傾僈僨僗傊 丂嘊丂傾儖僕僃儕傾偺傾僪儔儖偐傜儅儕偺僈僆傊 丂嘋丂儌儘僢僐偐傜儌儘僢僐椞僒僴儔偺僎儖僞僛儉乕儖丄儌乕儕僞僯傾偺價儖儌僌儗儞丄僰傾僋僔儑僢僩丂 丂丂丂僙僱僈儖偺僟僇乕儖傊丅傑偨偼傾儖僕僃儕傾偺僥傿儞僪乕僼丄儌乕儕僞僯傾偺價儖儌僌儗儞丄僰傾 丂丂丂僋僔儑僢僩丄僙僱僈儖偺僟僇乕儖傊 丂嘍丂傾儖僕僃儕傾偺僕儍僱僢僩偐傜僯僕僃乕儖丄僠儍僪傊丂巹偼丄擄堈搙偑斾妑揑掅偄嘆乣嘊傗丄傎偲傫偳柍棟偲巚傢傟傞嘍傪旔偗丄嘋傪慖傫偩丅暔壙偑崅偔丄偝傜偵桝擖晹昳偼崅偐偭偨僈儞價傾偱偼丄傗傓偵傗傑傟偢丄僐儞僞僋僩億僀儞僩摍偺怱攝側晹昳傪偨偔偝傫攦偭偨丅嵒敊偺戝敿偼掅懍偱偟偐憱傟偢丄傑偟偰傗倁倂偼嬻椻偺偨傔僄儞僕儞偑夁擬偟傗偡偄偺偱丄嬻婥庢擖岥傪傂傠偔偟偨丅
 |
 |
 |
 |
 |