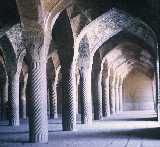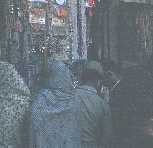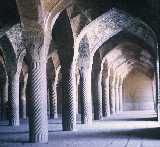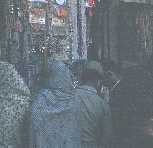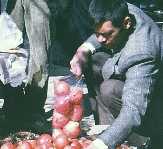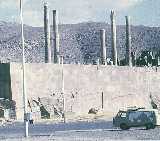アジア②(イラン〜パキスタン)
46.シラスの南の断崖 47.モスクの回廊 48.モスクの外壁 49.チャドルを羽織る女 50.同左
46.人類最古のシュメール文明を育んだ、チグリス川とユーフラテス川が合流してペルシャ湾に注ぐ岸に、古い町アバダンがある。対岸はイラクのバスラ。そこから、最新鋭の工業地帯バンダルホメイニ(旧バンダルシャプール)、それからザグロス山脈に入って、遊牧民や民族衣装で通学する女学生に気を取られながら高原の古都シラスへ。身体は常に汚れているので、町に入る前には、たいてい水場を探して手足を洗い、身だしなみを整えるのが私のマナーである。かつての旅人は写真ような崖を徒歩、ロバ、ラクダ等で苦労して越えたと思うと、”車や車道のありがたさ”とともに”苦労してやっとたどり着く喜びが失われた”ことに複雑な想いがする。
47〜48.古都シラスにくると、久々に雲があった。美しかった。アラブ人がインドのボンベイに雨を見にゆくと聞いたが、本当かもしれない。アラブのことわざに”雲は言葉、雨は行動””生木の小枝は曲げても折れないが、枯れ木は折れる”といった含蓄のあるものがあり、興味をそそられる。イスラム文化が凝縮された寺院の形や模様にも、目を見張るものがある。一般的には幾何学模様と草花模様で、動物や人は描かれていない。有名なペルシャじゅうたんも同じである。シラスには、詩人ハーフェーズやサーディのお墓がある。
49〜50.7世紀頃につくられたイスラム教の聖典コーランは、114章からなる。唯一最高神アッラーへの絶対信仰を基とし、啓示録たるそのコーランと天使・預言者・復活・審判等の信仰および告白・1日5回の祈祷・喜捨・断食・聖地巡礼等の勤行を厳格に守るイスラム教信者の女性を、写真に撮るのはもともとマナー違反だが、身体を隠す衣装チャドル(ブルカ)の開放度で、カメラをむけてよいか悪いか判断する。男性では、写してくれ、という者もいた。当時は、西欧化を急ぐパーレビ王政権時代で、都会の若い女性は、化粧や衣装からフリーセックスに至るまで、欧米化していた。今はイスラム文化に回帰したが、若い男女の志向は明らかにインターナショナルのカマンセンスだろう。
51.モスク 52.ザクロ売り 53.ペルセポリス遺跡 54.ダリウス大王謁見 55.同左
52.原産地だけにおいしい。1枚100万円以上はざらのペルシャじゅうたん。その渋い赤色は、このザクロの汁で染めたという。
53〜55.シラスから56km北にゆくと、ペルセポリスの遺跡がある。古代ペルシャのアケメネス朝時代の、紀元前522〜486年まで在位したダリウス大王は、アレキサンダー大王に敗れるまで、西は地中海から東はインドまでの全オリエントを支配した。518〜512年に建造された神殿・宮殿跡は、さらに約50km北のペサルガダエの原型遺跡とともに、往時の威光をしのばせる。石を敷き詰めた床を裸足で歩くと、往時の人も味わったであろうと思われる、ヒンヤリした感触がなんとも心地よかった。ただし、石のレリーフを見ると、高貴な人は立派な靴をはいていたが。
56.遺跡のたそがれ 57.イスファハーン 58.市場入口のフレスコ59.絨毯のクリーニング60.主食ヌン屋さん
56.当時の”王の中の王”といわれたシャー・パーレビ王は、世界の有力者を招待して、ここで建国2500年の華やかな祝賀会を開催した。後に、政権を奪われエジプトで果てた。これからも、アジア街道ではさまざまなドラマが繰り広げられるだろう。
57.日本流にいえば京都のような古都で、かつて”世界の半分”と喧伝され、栄えたイスファハーンの寺院の夜景
58.戦国絵物語が描かれている古いバザール(市場)の壁。日本文化にも影響を与えた面が少なくないイランでは、昔の文化をしのばせる美しい絵をたくさん売っており、男女の交際がのびやかだった様をかいまみる。美人が多い。
59.古いじゅうたんの、クリーニング方法の一つとか。
60.焼きたてのパンはどこでもおいしいが、冷えたヌン(トルコではアクメック)は固くて---紅茶につけてたべる。
61.ヌンのつぼ焼き 62.鍛冶屋 63.染色、乾燥 64.活気がある市場 65.同左
61.土づくりかまどの内壁にヌンを張りつけて焼く。
62.アジアの家内製手工業は、まだまだ健在である。中南米、アフリカも同様である。
63.染色後は、やがてじゅうたんになるのか?
66.寺院の模様 67.寺院の遠景 68.コム? 69.同左 70.同左
66〜67.イスファハーンの寺院
68〜70.宗教都市といわれる聖地コムでは、イスラム教徒以外の立入を禁止していた。
71.寺院の壁画 72.コムの金色ドーム 73.交差点の記念碑 74.テヘラン市内 75.カスピ海の魚?
71.寺院の壁画には、珍しく鳥が描かれていた。
73.故パーレビ政権が建立した、首都テヘラン郊外シャー・レザ(パーレビ王の名)通りのモニュメント
74.テヘランの交通渋滞は、世界一クラスであった。その他、世界で酷かったのはナイジェリアの首都ラゴス、ヨルダンの首都アンマン、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス、ベネゼエラの首都カラカス。背後は雪山のエルブルス山脈
75.鯉に似た魚は、カスピ海で獲れたものか。カスピ海の水面高度は海抜マイナス28m。湖面の広さは日本とほぼ同じで、世界最大である。塩湖で、キャビアになる魚卵を持つチョウザメがいる。首都北部の湖岸では、稲作もおこなわれている。
76.盗難に遭う 77.ヌンのみ生活 78.ベーナム夫妻 79.パキスタンのカラチ80.ネハラ・オマール家
76.旅にでて丁度7年目の12月2日、うす暗くなった夕刻、テヘランで会ったアメリカ人に招待されてレストランにいった。食後、車に戻ると、三角窓のガラスが割られていた。一瞬、盗まれたー!!と思った。車のサイドドアーを開けると、鍵をかけていたのに、開いていた。これで盗難の確率は、ほぼ100%だと感じ、身体の力がぬけていった。調べると、全資金約5000ドル(現金はドルとドイツマルクで約1500ドル相当)、カルネ、フイルム3本、背広2着、ズボン、寝袋、毛布、スーツケース、ラジカセ、トランジスタラジオ、フラッシュライト、歯のレントゲンフイルム、車の修理本---がなくなっていた。
最大の失敗は、ちょっとのつもりで、正規の駐車場に止めないで、暗い路地に止めたこと。盗難は必ずあるので、もし入られたらと、わざと盗ませるための手提げ金庫を用意して、わざとチャチなチェーンで車体につないでおいたのだが、つい全財産や重要書類を入れておいたことだった。アフリカ大陸ではちゃんと実行していたのに---小才あまって思慮足らず、か。生来のいい加減さが、逆に災いを招いてしまった。産毛まで白髪になるかと思うほどのショックを受け、旅の継続を一時は断念した。ここでは、1600年間もの由緒ある家柄を引き継いでいる、上院議員アラメ氏(70歳)の奥さんにも手助けしてもらったが、盗品はかえってこなかった。
ただ、自分に気合を入れて、「精神まで盗まれたわけではない。腐るな!」と叱咤しつづけた。
77.ポケットに残っていた小金で毛布を買い、マイナス5度の雪ふる車内で風邪をひいて寝こみ、食事はヌンだけの、みじめな生活に一転した。ここでは、旅行小切手といえども、一時に大金の再発行には大変な時間と労力がかかる、ということがわかった。ただ、旅行小切手は数社にわけてつくっていたので、約1000ドルは2週間後に得た。
78.塗炭の苦しみのなかで、またも親切な人々に助けられ、苦境を脱することができた。JALのテヘラン支店に勤務するベーナム夫妻の奥さん(旧姓ナカタ・マサコさん)は、「家には2間あるし、駐車するスペースも近くにあるので、よろしかったらいらっしてください」と。夫は日本に留学したことがあり、一家の好意に甘えて、再発行のカルネがベルギーから届くまで、何かとお世話になった。娘さんを囲んで、左端は夫の妹さん、右端は夫のパルビスさん
79.イランでは、ビザの有効期限内に、旅行小切手の再発行の見通しがたたなかった。旅行小切手会社の本社があるニューヨークと何度も手紙、電話、テレックス等を取り交わしたがダメだった。こういうときのお客は弱いものである。真冬の路上の車内で、しかも毛布1枚では、服を着て寝ても寒いし、心配事も重なって眠れなかった。やむなく、再発行小切手の受取地を、暖かいパキスタンのカラチに指定して、ビザが切れる前に、パキスタン中部のケッタに向った。憂鬱な気分でテヘランを後にし、雪道から脱出しようと南下していると、突然、左後部のタイヤがホイールとともに外れて吹っ飛んだ。雪道では、紛失した小さな止めボルトを探すのに苦労した。南部の砂漠では雪も消え、カナートの位置を示す盛土が、えんえんと続いていた。砂漠の地下に水脈が走り、カナートという太古からの水路が、オアシスまで続いていた。
パキスタンのバルチスタン砂漠は無舗装・無人で、灼熱の太陽と草木一本ない乾燥した大地と、ときおり左右に、陽炎にゆれるはげ山が見えるだけである。幸い、ソフトサンド地帯は少ない。たまに、道路脇に延々と続く塩の結晶や、たまに見かける遊牧民が救いだが、360度は地平線で、単調きわまりなくイライラしてくる。このような地だから、右手に1つだけあったミナレット(回教寺院の外郭に設ける細長い尖塔で、祈りの合図や祝祭日の明かりを灯す高い塔)を望見したときは、感動した。たった1つの人口構築物が、単調さという渇きを、十分にいやしてくれた。さっそく停車して、砂漠横断の無事と、旅行小切手の再発行を祈った。(後に、この砂漠で、原爆実験があった)
ケッタは、山のふもとにある古い町で、若い旅行者には人気がある。長期滞在者もいた。麻薬中毒者もいた。気候は暑くも寒くもなく、かといって雪も降るし乾燥地帯でもある。品物はそこそにあり、人々は素朴で、2〜3万円あれば、1か月を快適に暮せそうで、気に入った。ここでは、警察署に駐車させてもらい、汽車に21時間乗ってカラチにいった。財布は軽く、汽車なら安いからである。
80.ここでも、すばらしい人にめぐりあい、なんと今度は誕生日に、残金の2200ドルが再発行されたのである。
私の旅の師匠であるマイケルは、旅行中に事業で成功したカラチのオマール氏(航空機事故死)の世話になり、私はマイケルから住所をもらっていた。そこで、テヘランから手紙をだし、ケッタで電話をすると、温かい返事があった。イスラム教徒の未亡人が、ただ夫が17年も前に面倒を見た単なるベルギー人旅行者の、その友人で、一面識もないのに---心から感謝する次第である。なお、銀行では「ドルでは渡せない。ルピーなら発行する---」といって当初は不可能だった。だが、あらかじめネハラさんは、銀行の知人に助力を頼んでおり、私の抗議に、この女性は懸命に味方してくれ、上司を執拗に説得して、やっと再発行されたのである。男と対等に渡り合う、そのパキスタン女性の迫力に、圧倒された。お礼にケーキを買い、ネハラさんの母も含めて一家と祝った。
この後、人類最古の文明の一つといわれる、インダス河沿いのモヘンジョダロの遺跡に寄り、写真も撮ったがフイルムは日本に届かず。紀元前3000〜1800年頃の遺跡で、レンガづくりの約3万人の都市跡、見事な上下水道設備、権力者・神官を表したような出土品、解読が待たれる文字、鉄器、現代の物と同様のサイコロ、チェス道具、綿、小麦、---と目を見張るものがあった。遺跡化の原因は、インダス河の水位が下がった、地盤沈下が起きた、疫病が蔓延した、と種々あるが、「レンガを焼くために、樹木を伐採しすぎた?」ともいわれている。現代にも通じる警告が、紀元前にすでにあったわけで、樹木を燃料・家屋・家具・紙・軍事物資等用として伐採して、危機的状況に陥っている所は世界にあり、人口の増加とともに解決策が望まれている。平野の樹木はなくなり、ヒマラヤ山脈やアンデス山脈の高地にかけあがるハゲ山、サハラ砂漠の拡大につながる遊牧民等の伐採、アマゾンやコンゴ盆地のジャングルを開発する焼畑---。緑の大地は、やがて褐色になるのか。
チャイハナ(食堂)で、「どこの国の人が、最も多く訪れるか」と、質問すると、「ドイツ人と日本人。ドイツ人は、飛行機でくる中高年者も多いが、日本人は汽車等でくる若者しかこない」という。今でも、遺跡から発掘された牛車の車輪と同じ原始的な形状(横から見ると交通標識の進入禁止のような形で、丸い輪に一本の輻=や)の車輪が村を往来しているので、まさにタイムスリップをしたような錯覚に陥いった。おまけに、店主から「日本は日の出ずる国だから、ここより暑いだろう」と聞かれたときは、あ然として返答に窮した。一般的には、みんな親日的である。ここでは「使い古したカレンダーでいいから、日本のをおくってくれ」と哀願された。家屋を飾るものが少ないだけに、着物姿等は大人気である。カラチのボデービル道場には、日本のプロレスラーの写真が掲げられており、のぞいていたら、ただ日本人というだけで、甘い紅茶をごちそうしてくれた。
それにしても、ケッタとカラチ間の列車の旅はすさまじかった。ケッタ駅では、多くの乗客が一度に押しかけて席を奪い合うから、戦争のような状態になった。駅には”アリが行列している絵柄のポスター”が掲示してあり、現地語が添えてあった。意味が不明で心にひっかかっていたが、これで意味がわかった。じつは、彼らは順番をつくるために行列する、ということを知らないのである。または、知っていても力ずくがまかり通る世界か。さらに、Cibiという町では、現地人も驚く最高気温52.7度を記録した日の列車内は、凄かった。荷物棚はすべて寝床になるほどの混雑・ホールドールという身の回り品すべてを入れた旅行用袋の山・冷房はないから開け放した窓からのほこり・ほこりっぽいから皆が床につばを吐く・合唱・食事・お祈り・子供の泣き声・けんか・便所にゆけないからその辺で---と、アジアを十分に堪能した。
一方で、この列車にはサッカーチームの貸切客車と女性専用の部分があったが、こちらは空いており、まるで天国のようだった。
ケッタからはハゲ山の峠を越えて、眼下のアフガニスタンの砂漠に下りてゆく。尾篭な話で恐縮だが、お山のてっぺんでのトイレは最高だった。はるかかなたで、陽炎にゆれる広大な砂漠を眼下に見て、心地よい風にお尻をなでられながらするトイレは---言葉ではいい表わせないほど気持ち良かった。狭い便所しか知らない方には、ぜひ、体験をおすすめしたい。