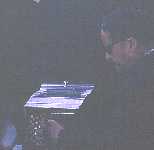中南米②(エクアドル)
41.郊外の市場 42.パナマ帽の本家? 43.装飾品はいい 44.アンデスで吹く笛は 45.何用の壷?
41〜45.郊外のメルカード(市場)を訪れると、バケツに入った蜂蜜が売っていたり、物珍しい光景にしばし時を忘れた。パナマ帽の本家は不明だが、「高価なパナマ帽は、エクアドル原産のパナマ草の葉を、インディオが月夜のみに編んでつくった」といわれている由緒あるもの。オタバロ村等の、主にインディオが住む地にゆくと、土づくりの家にはニワトリやヤギ等が一緒に住み、台所・居間・寝室等は渾然一体となって雑音が皆無で、まことに質素である。そのような土臭い中で、日本製の足踏みミシンと乾電池式トランジスタラジオが印象的だった。そして、夕方からは神秘的な雰囲気が漂う。電気・ガス・水道・電話---のない世界だから当然だが、太陽が山陰に沈むと、集落は真っ暗になり、夕食を済ませたあとの土間の火だけが、赤々と輝いていた。灯油ランプで明かりがある家もあるが、例外であった。あたかも、一昔前の時代にタイムスリップしたかのような、幻想的な光景にしばしうっとりした。この平和がいつまでも続くように---と、祈らずにはいられなかった。
46.純手作りロープ 47.音楽隊 48.授乳中、ごめん! 49.伝統と異文化の交差50.安くてうまい食堂
46.インカ時代には、小さなヒモの結び方で言語が表現され、支配下の広大な部族の統治に使われた。アンデス山脈をかけめぐったメッセンジャーは、このヒモを携帯し、これに織り込まれた言語で意思疎通をしたという。
51.たまには肉もいい 52.食用のクイ 53.種の選定 54.何の毛? 55.農具の柄?
51.寒いし、売れゆきはよいし、屋外でも腐らない。保健所の検査は---かたいことはいわない。
52.スペイン語でCUYといい、げっ歯類ネズミ科で、食用として、インディオの家庭では、よく家畜の一つとして飼っている。日本語でもクイ、と上野動物園では説明してくれた。
53.わきに抱えられたニワトリも、食べたそ〜う。
54.リャーマの養育種の、アルパカの毛か。ビクーニャはより高価なので、主にヨーロッパ等に空輸されてしまうから、ここにはでないだろう。
55.スキの柄でしょうか?
56.本当にメス? 57.伝道師? 58.花売り 59.おしゃれな婦人 60.果実屋
56.ひよこ売り
57.みんなが神妙な顔をしているし、寄付箱のようなものがあるから伝道師か、何かの語り部か。
60.手前のバナナ状をしたプラタノは、主食の一つで甘くなく、油であげたり、煮てつぶして食べる。他の主食には、米・麦・ジャガイモ・トウモロコシ等があり、低地に行くとマンジョウカ(アフリカではキャッサバという)がある。ちなみに、今では中南米のどこにもあるバナナやプラタノは、コロンブスがアメリカ大陸にきた当時はなかったといい、遺跡からも発掘されていないという。
61.ねぎ屋 62.ジャガイモ屋 63.魚屋 64.コロラド・インディオ 65.赤い染料
62.さすが原産地だけあって品種が豊富で、これはスープ用、これは料理用等と教えてくれた。厳密には500種類もあるといい、原産地を同じくするトウモロコシと唐辛子等がなければ、地球の人口は現在よりはるかに少なかったであろう。長年のインディオのご努力に、敬意を表したい!!
64.バナナ等が茂る太平洋側の暑い低地にゆくと、彼らの集落がある。本当の部族名の分類は不明。観光客を生活の糧に上手に取り入れており、撮影料を要求するので5スクレ(56円)渡したら、納得していた。ただ、観光客相手の商売のときは、腕の高級腕時計はない方がよいのだが---。それとも、「自分達は観光客と対等だ」という主張か。
65.木の実をつぶして、赤い染料をつくる。
66.寝床 67.坂道脱出 68.町にでる 69.タクシー乗り場 70.町で用事をたす
66.コロラド・インディオの寝床
67.雨で赤土の急坂がすべり、スリップして登れなかった。そこで急きょ、先のモデルに手助けをたのみ、路面に小枝やバナナの葉を敷き、車を反転させて前輪駆動にして、いきおいをつつけて後進で駆け上がった。
68.自転車等はないから、長い距離を徒歩か車等になる。
69.タクシーは、これを見越して近くで待機している。
70.便利な物が手に入る町はよい。金と物との生活に組み込まれて行くのは、時間の問題か。
71.コロラド青年 72.釣いかだ 73.同左 74.同左 75.日本人渡来説
71.正装して颯爽と町を歩く姿からは、誇りを感じさせる。
72〜74.グアヤキル港の南の、プラヤ村の浜でキャンプ。世界一軽いという木の「バルサ」でつくったいかだ(スペイン語でいかだもバルサという。BALSA)に帆を着けた漁船で、一本釣りをするというので、漁師に頼み、釣りにゆくことにした。早朝にでるというので、前夜は遅刻しないようにと、寝ずに午前0時から浜辺で待ち、結局、午前3時半に出漁。(正確に出発時間を聞けば、少しは眠れたのに、南米流のアイマイな流儀になってしまったのか)いかだにまたがって、一本釣りにでかけた。ところが、釣り場に着く前に、寝不足もあって、強烈な船酔いに襲われダウン。しばらく耐える私に向かって、何度も、笑顔の漁師がいわく
「SEIS HORAS MAS,O TIERRA」(船酔いに耐えてさらに6時間頑張るか、または陸に戻りたいか)と。
残念ながら答えは「すみませんが、陸に戻して欲しい」。親切にも、40スクレ(450円)で乗せくれ、私の船酔いで、この日の漁を台無しにしまった。相手からの要求はなかったが、休業補償をすべく、さらに50スクレ(560円)を渡して、勘弁してもらった。船酔いで体調を崩したのを戻すため、浜辺でエビを1kg6スクレで買って、塩ゆでして食べた。
75.1972.4.17、アメリカ・カリフォルニアのテレビの特別番組で「コロンブスがアメリカ大陸を発見するずっと以前に、日本の漁師達(南方から黒潮海流に乗って北上してきた「港川人」?)が、南米のエクアドルあたりにきたふしがある。エクアドルの太平洋岸のグアヤキル港の西方のバルディビア地方の遺跡から発掘された土器や骸骨等を調査し、日本のと比較した上での発表である」という。そこで同国にいったら少し調査してみようと思っていた。首都の国立博物館を訪れ、館員との会話で、この話の信憑性を確認した。そして、太平洋岸の遺跡からでた土器等からの発表ということで、アンデス山脈西側の低地ジャングルに住むインディオ・カヤッパに、もしかして日本人の血がつながっていないかと、カヤッパ・インディオを訪ねることにした。ただし、道路地図もまともにない国(当事はカラー写真もなし)だから、ジャングル内の地図はなく、何らかの手がかりがないかと陸軍に赴き、航空写真だけは複写してでかけた。この話を日本大使館の一等書記官に話したところ、興味を示していた。後に、ペルーの首都リマの、インカとプレインカの土器等を豊富に展示した、アマノ博物館のアマノ館長と話したとき、これらの説は当然知っており、興味深い会話に花が咲いた。また、帰国後、東大のこの種の研究室の方に尋ねたところ「現在のところ、この説は肯定も否定もされていない」と、学者風な返答だった。
76.出土したハニワ? 77.帆かけイカダ等で 78.埋葬された土偶 79.カヤッパ河口 80.小舟で川を遡る
76〜78.紀元前3200〜1800年頃のもので、東洋風のものがあり、それらは日本の九州の出土品と似ているという。日本政府から贈られた土器も展示している。頭蓋骨にも似た特徴がある、という。なお、インカ時代の土器には、酒を注ぐと素敵な音がしたり、遊び心がふんだんにちりばめられたものが沢山あり、当時の文化度、繁栄度が垣間見れる。現在の"レモン絞り器”とまったく同様のものもあり、驚いたが、これについては「中東のトルコ・アンタキアのローマ時代の遺跡の出土品」でも、同様の器を見ており「どの民族も考えることは同じ」と感心させられた。
77.帆かけイカダは、ノルウェー人のハイエルダール氏が、エクアドルから南太平洋を渡って実験したコンティキ号にそっくりである。当時の海流が、日本からエクアドルに流れていたのではないか、という説もある。ベーリング海峡は今でも、年間の3分の2の期間は結氷して閉ざされているが、当時の気候や閉鎖状態から、今よりずっと短時間で東洋から中南米にゆけたのかもしれない。
79.すべてを押し流す、熱帯下のカヤッパ河口
80.1カ月かけて、ジャングルで大木からくりぬいた小船。これを1本のカイで漕いで、途中の空家に泊まりながら、3日間さかのぼる。
81.川岸の高床式家屋 82.蒙古斑 83.言葉を録音する 84.家族 85.日用具
81.適度に点在して、川から魚やエビ等を、ジャングルではバナナやプラタノ等を、家屋の下では豚やニワトリ等を飼って生活している。たまにジャングルでラワンの大木を切り倒し、中をくりぬいて小舟をつくり、これに独特の模様をつけて800スクレ(9000円)で売って、生活必需品を買う。
82.日本人の生後1年以内の赤ちゃんには、99.5%が身体のどこかにでて、やがて消える。この班は、単に彼らが属するケチュア族が蒙古系だからか?
83.カヤッパの子供達が協力的で、話す言葉を録音した。
84.原始社会で着られていた貫頭衣が発展したものか?中南米で多く見られる「前が割れているポンチョ」、「頭からかぶるルアーナ」も似ているが、これはヨーロッパからも持ち込まれたものか。
85.灯油ランプと、樹皮をたたいて柔らかくした布。河口のリモネス村の中学校で、単身学んでいたカヤッパの青年は、この樹皮布を毛布代わりにしていた。
86.かまど 87.流し場 88.主食プラタノ 89.雲上のキャンプ 90.船外機付カヌーで
86〜88.カヤッパ族探訪記の続きは、フロントページの別の項にする予定です。
89.今度は、アンデス山脈東側低地の、アマゾン・ジャングルに猿狩を見ようといった。同じケチュア族に属するコファン・インディオの村に、通訳もかねたチリの青年ホセ・アントニオ・エスコバル・ファーストといった。海抜4100mの峠近くでニジマス釣りをしたら、ミミズでは4匹、釣ったニジマスの卵では15匹釣れた。空気が薄くて火が燃えにくいので、予備ガソリンをかけたら爆発して、やけどを負うところだった。
90.船着場では、村人が体長30〜40cmのジャガ−の子供を持ってきて、「そのカメラ(ハーフサイズ)と交換しよう」といっていたが、断った。小さくとも、うなり声えはまさしく密林の王者だった。
91.川岸の高床式家屋 92.泊まった家 93.私達を見送る女性達 94.首都キトの祭 95.同左
91.アンデス山脈西側のインディオ・カヤッパと同じように、ここでもアグアリコ川沿いにコファン・インディオの高床式家屋が散在し、似たような生活をしていた。ただ、この村は、以前から近隣の村との経済関係があったのか、スペイン語を話す人が多かった。
92.パシリオさんの家。まずは、発酵したプラタノのスープで歓迎されたが、下痢しそうだったので急いで薬を飲んだ。チリ青年は飲まなかったためか、その後はしばらく猛烈な下痢に苦しんだ。持参したトイレットペーパーは、早くも彼がすべて使ってしまった。夜は、蚊等の襲撃で眠れず、カヤをつったまではよいが、ヤシの樹の幹を割って敷いた床の、その割れ目から得たいの知れぬ虫がでてきて、身体中を食われ、暑さ・痛さ・かゆさで熟睡できなかった。子供達はみんな身体中に食われた跡があり、これに耐えられた子供のみが成長するのだろう、と思った。しかし、ここでの体験はすばらしかった。
釣りの餌はミミズだが、ジャングルの柔らかい土を掘ると、小指ほどの太さで長さは約1m。長いのになると2m余もあるという。これを餌に、マグロ釣りのはえ縄漁で使うような、大きな釣針にかけ、川に突きだした樹の枝に道糸を縛って、仕掛を川に沈めておく。翌日、道糸をたぐると、歯がするどい5kg位の魚がかかっていた。
食用のための猿狩にゆく前に、吹矢の腕前を見せてくれた。木をくりぬいた長さ2m位の真直ぐな筒と、長さ20cm位の細い竹矢を用意し、竹矢の後部に軽く綿をまいて筒に差しこみ、筒を目標に向け、強く吹く。狩猟時は、竹矢の先端に、幼虫や木の根から採った毒液をぬる。みんなは、約20m先のバナナの幹に命中して見事だったが、私がやると両手で長い筒の片側を支えるのは重く、吐く息は弱く、慣れないので当たらず、届かない有様だった。しかし、これでみんなとの親交が増し、誤解などから思わぬハプニングも予想される、心細いインディオ生活体験を安全なものにしてくれた。
猿狩は、まずジャングルの湿地帯を歩く。パシリオさんは裸足で、私達は長靴だった。1km位歩き、高さ10〜50mの樹の上にいるのを吹矢で落とすのだが、まずは鳴き声を真似して呼び、居場所を探す。鳥も同じ。やがて、吹矢があたって落ちてきた猿には、赤ちゃんがしがみついていた。
途中で蜂の巣を発見したときは、たまたま蜂が留守だったので、3人で手を蜂の巣に突っ込み、乾いたのどを甘い蜂蜜で潤した。
小川を渡ったときは、パシリオさんが「あそこに、尻尾に毒を持ったエイがいるから気をつけろ」という。よく見たら、隠蔽色でわかりにくかったエイが、川底でじっと獲物を狙っていた。淡水のイルカもいるアマゾン河だが、ここは大西洋から約6000km。ここの水は6か月かかって海にたどりつく。その源流の小川に、淡水のエイがいるのである。
村に帰り、はしゃぐみんなに捕った親猿の丸焼きを一部進められた。だが、かわいそうで、私は「腹の調子が悪い」といってやんわりと辞退した。傷がついていない赤ちゃん猿は、ペットとして飼われることになった。オームは1時間半煮ても固くて、歯が立たなかった。今はみんな鉄砲や散弾銃を持っているので熊、猪、鹿、狸、カピバラ、猿、オーム、ジャガー等の獲物は少なくなって、1週間以上も遠出をしないとたくさん捕れないという。夕方、獲物の鳴き声が聞こえると、パシリオさんは緊張した面持ちで、銃を片手にジャングルに分け入っていった。
ただ、この平和な世界でもオイルが発見され、様相は急激に変わりつつある。当初は、油田開発にともなう強制移動に反対したコファン・インディオ等が紛争中に殺戮されたり、移動を余儀なくされたり、文化文明は怒涛のごとく押し寄せているのである。油井柱はあちこちに数百本立って、上空には大型ヘリコプターが飛来し、無料で配られた日本製トランジスターからは「さあ、エクアドル語を勉強しましょう。わたくしはエクアドル人です---。」と、流れる。地下4000mから噴出した熱い原油は、パイプで海抜3000〜4000mのアンデス山脈まで押し上げられ、そこから下って太平洋の港からは、日本へも輸出されているのである。
93.向かって左から3人目の、横を向いている少女が、パシリオさんの娘。とても可愛い愛嬌のある子である。足の傷が化膿して、片足を引きずっていたが、何もできない自分がはがゆかった。
96.首都キトの祭 97.同左 98.同左 99.峠の聖母マリア像 100.クイ売買
99.高山は空気が薄く、エンジンのかかりが悪い。運転中でも、回転数が落ちる下りではたびたびエンジンが止まった。こういうときは、ギアーをローにして、急にクラッチを合わせて再始動させた。トイレ等で車を止めても、エンジンは止めず、アクセルに水タンク等の重しをのせて、軽くふかしておく。宿泊するときは、坂道の上にした。リャーマやアルパカの毛で編んだセーターは、暖かい。
101.市場の村人 102.帯売り
101〜102.インディオは、種族毎に衣装が違う。アンデス山脈の東西に遠く離れて住む部族でも、生活様式は似ているが、言葉は違う。町では異なった種族が見られるが、田舎では単一のインディオしか見られず、住みわけができているようだ。リオバンバ村のインディオは「リオバンバ・インディオ」と呼ばれている。