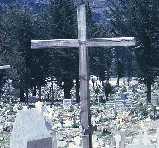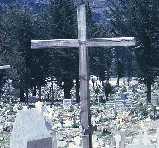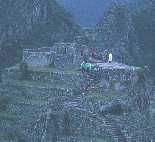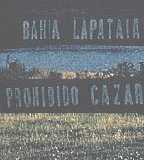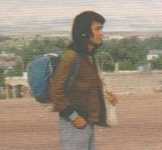中南米③(ペルー以南)
106.旧ユンガイ市 107.廃墟の旧教会 108.橋なし川 109.ペルーのトヨタ工場110.アンティコーナ峠
106~107.1970年、アンデス山中のウアラス地方に、震度7の地震が45秒も続き、約6万人が死亡。傾斜にあった旧ユンガイ市は、山肌が崩落して土づくりの家屋と多数の人が埋まり、掘り返すのは不可能に近く、そのまま墓地になった。日本でも、活断層の上に暮す人は、対岸の火事ではすまされまい。
108.世界では、いやというほど橋のない川を渡らなければならないが、こういうときはまず車を止め、川に歩いて入って深さ・流れの強さ・川底の突起等を調べてから渡る。油断して甘く見ると、ときどき大石や陥没穴で車を傷める。車高の高さや積荷の重量には、細心の注意が必要である。無理と思われるときは渡らず、待つか迂回する等、他の方法で対処する。
109.川崎社長からは、車がVWにもかかわらず、カーラジオとフォーンを無料でつけてくれ、「たまには思いだしてくれよ」と。旧ユーゴスラビアでは、地元のヒッチハイカーにトランジスタラジオを盗まれてからラジオを買う予算がなく、そのため土地の情報が限られ、音楽も聞けず、さびしい思いをしていたので、大変助かった。助けてくれた、やさしい人々はさらにいた。本来なら、物心両面でお世話になった出発前の方々、世界中でお世話になった他の日本企業の方々、および地元の方々に再度お礼を申し述べたいところですが---、この場を借りて、改めて、心よりお礼申し上げます。
首都リマでは、ビーチサンダルを「サヨナラ」(トルコでは「トウキョウギンザ」)とロマンチックな名で呼称していた。街中で、マンション風の前に駐車していると、「今日はクリスマスよ」といってお菓子をくれたセニョリータもいて、チャーミングな町である。この国では、日系人の食堂に入ると無料にしてくれたり、沖縄出身が多い日系人からは、いろいろな好意を受けた。
110.鉄道が通る所としては、最も高いこの峠は海抜4818m。高山では、酸素が薄くなるから、平地と同じ動き方では、ものすごく苦しくなる。たまに忘れて、パンクタイヤ交換後、小川におりて汚れた手を洗い、駆け足で元に戻ったら、呼吸困難に陥り、死にそうだった。
走行中も問題が発生した。登りは、アクセルを適当に踏むからいいが、下りは危険だ。アクセルを踏めば速度がつきすぎて危険だし、曲がりくねった下りは、速度をだせないからエンジン回転数が落ちる。すると、エンジンが止まる。止まらないようにアクセルを踏むと、また速度がですぎて危険になる。結局、「アクセルとブレーキとクラッチを同時に踏んで」この難関をのりきった。クラッチの磨耗は、大きかったと思う。オートマ車なら、事前に何らかの対応が必要だろう。
こんなことに気を取られていたら、山中で突然車が前進できなくなった。エンジンは回転し、クラッチも入っているのに、である。調べると、ブレーキドラム中央の溝が磨耗して、回転している車軸とのかみ合わせができず、車軸の動力がブレーキドラム→タイヤに伝わらなかったためであった。やむなく、閑静な山に向かって、付近に住んでいるインディオを呼び、きてもらい、「クスコで部品を買って帰るまで、ここで数日間見張りをしてほしい。留守番料は---」と頼んだ。結果は、247km先のクスコから3日目に戻り、すべて解決した。しかし、この1件は反省すべき点がいくつかあった。ブレーキドラムの中心部からは、事前に磨耗してできた黒い粉が見られていたのに、鉱山地帯の黒い泥だろうと軽く見て、その原因を究明していなかったのである。酸欠で頭が朦朧としていたこともあったが、ここでも、いい加減な性格が災いを招いた、と思う。重い車での山道走行は、タイヤのボルトをしっかり締め、毎朝確認することである。
111.インカ時代の城壁 112.隙間がない城壁 113.天然のすべり台 114.マチュピチュ遺跡 115.遺跡は山頂に
111.クスコは、わずか約70年間のインカ帝国の都だった。当時は鉄器・鉄砲・火薬・馬・紙幣等・文字・税金(代わりの労働はあった)等がなく、それでも王はアンデス山脈界隈を数千平方kmも支配していたという。誰でも結婚すれば土地があたえられたという、うらやましい時代だった。城壁に水時計らしきものもあり、往時を忍ばせる。土産物屋を歩くと、古色ゆかしい品々が多く、貧しい私でも購買意欲を刺激される。
112.鉄器もない時代に、どうして隙間がない「空積み」城壁が作れたのかは、まだ謎だという。
113.インカ時代もそうだが、以前の長い長いプレインカ時代からの、子供達のはしゃいだ声が聞こえてきそうだ。
114.発見されたのは近年で、どのような人が、何のためにつくった住居・神殿等で、なぜ滅びたのか、の定説はまだない。
115.断崖絶壁の下を流れるウルバンバ川は、やがて海抜3812mの世界一高い所にある大湖チチカカ湖に注ぐ。
116.水時計? 117.棚田畑 118.ピサック村 119.同左 120.同左
116.マチュピチュの遺跡は、いまも神秘につつまれている。
117.水路は、完全にひかれている棚田畑。ヒマラヤ山脈同様の棚田畑は美しいが、構築と作物の栽培は、骨が折れそうだ。
118~120.クスコ郊外のピサック村地帯は、インカ時代を彷彿とさせるほど浮世離れしており、考古学上重要な場所。時間が許せばじっくり見たい所である。
121.ピサック村 122.同左 123.同左 124.同左 125.同左
121~122.コカの葉は、麻薬のコカインの原料となるものだが「眠気を防止する、空腹をいやす」等の効用があり、市場で売られていた。よくインディオが、噛みタバコやチューインガムのように、これを噛んでいるのを見かけた。
123.ほら貝を吹き吹き歩く。日本の山伏の特許にあらず、か。
124.特徴ある棒と帽子が威厳を示す。
125.部族衣装がきれい。
126.ピサック村の市場 127.同左 128.踊りながら歩く人 129.チチカカ湖 130.アルパカ
128.何かの祝いごとでもあったのか、酔って歌って練り歩いていた。
129.海抜3812mの世界一高所にあるチチカカ湖。面積は琵琶湖の13倍もある。アシ(トトラ)で編んだ舟(バルサ)が情緒をかもしだす。アシを折り重ねた島もあり、その島で家畜さえ飼って暮らすインディオもいる。ピンクのフラミンゴが美しい。
130.リャーマ(=グアナコ)の畜養種アルパカは、ラクダと同じように、警戒するとピューとつばを吐いて威嚇する。同じラクダ科のビクーニャは、海抜3700m以上位の所に棲息し、身体はアルパカより小型で、その毛織りは温かいので1kg5万円もする。ペルーの高地では、野生のビクーニャ捕獲はチャクといって、重要な収入源になり、またビクーニャの糞は咳止め、気管支炎に効くという。
131.ボリビアの首都 132.同左 133.チリのプエルトモン 134.空地を占領 135.パンパ=平原
131.海抜3600mの高原にぽっかり穴があいたような、すり鉢型の大きなくぼ地があり、その底が実質上の首都ラパスで、背後の雪山はイリマニ山で海抜6490m。ラパス(平和)といっても泥棒は相変わらずで、夜間にバックミラーを盗まれそうになり、追いかけたら、高地のため心臓はガクガクして、張り裂けそうなった。あきらめ、呼吸を整えて床に着いたら、翌朝バックミラーはなくなっていた。警察にゆくと「泥棒市場があるから、そこに行って自分でさがせ」と知らん顔だった。中南米の高地では、どこでも同じ話を聞いたが、たまの休日は暖かい低地に行って身体をほぐし、濃い空気をたっぷり吸って鋭気を養うという。
132.くぼ地の底は、昔からの建物等がある繁華街と高級住宅地で、貧しい人々は郊外の傾斜地に広がっている。ただ、郊外の傾斜地は見晴らしがよい。
133.ボリビア→アルゼンチン→チリへ。草木がなく、殺伐たる高原の塩湖に、ピンクの羽が美しいフラミンゴがいるボリビア。南部は川に橋がないところが多く、その都度、川を渡る際の岩や木で車を傷めた。雨期(2月頃)は、通行不可能である。
アルゼンチンに入ると、まもなく低地の平原になる。暑くなり、夜はホタルが舞う。山間の避暑地メンドーサ市では、護身用に22口径8連発のリボルバー1丁と、弾50発を10ドル買った。不思議なもので、実際に重い銃を手にすると、「これで稼げば、簡単なのに---」等と物騒な感慨がひらめく。
チリ入国では、肝を冷やした。国境の役人に車内を見せると、彼はいきなりゴミバケツをつかみ、目前の深い谷にゴミを投げ捨てたのである。私は、ときどきゴミバケツの底に持ち金を隠していたので、一瞬、全財産が谷に捨てられたような、大ショックをうけた。このときは、たまたま別の所で、危うく難を逃れたのである。これらの所作は、アメリカのカリフォルニア州に入るときと同じで、野菜や果物も持込禁止だった。
ドイツ系が多い南部のプエルトモン港。車内でハマグリとムール貝を焼き、ワインを飲んで31歳の誕生日を1人で祝った。目前では、マゼラン・ペンギンがペアーで戯れており、ちょっぴりうらやましかった。ここから南極までのリアス式海岸は海産物の宝庫で、チリ人はけっこう刺身を常食していた。スペイン語でも柿はCAQUI=カキであり、店では売っていた。インフレ下にあり、外貨を持った人には破格の楽しい生活ができたから、有頂天になっていた。
ところが、首都サンチャゴへの帰り道に、なんとエンジンが割れ、オイルが亀裂から漏りはじめたのである。ボリビアでは、橋なし川で車底を傷つけ、エンジンを止めるボルト穴にヒビが入っているのを知ってはいたが---。当時は、故アジェンデ政権下で、軍人が国中に見張りをたてて物々しく、輸入品は極端に限られていた。輸入タバコを1箱買うのに、街区のワンブロックをまわるほど長い行列に並び、2箱欲しいならコミュニスタの新聞を買え、といわれた。VWの輸入部品はゼロ。このときは、部品を買いに外国にいってくるか等まで考えたが、持込むときの高い関税を考えると旅を断念せざるを得なかった。
眠れぬまま首都に戻り、ワラにもすがる思いで唯一の知り合いであるトニー宅を訪れた。トニーは、反政府活動で身が危うくなり、そのため外国にでて、たまたまエクアドルで一緒にアマゾン・ジャングルへ猿狩に行った青年である。その後、ベネゼエラにゆき、交通事故に遭ったという。チリにきて最初にトニー宅を訪れたときは、「トニーはベネゼエラ旅行中、オートバイが転倒して入院中」で帰国していなかった。
ところがなんと、タイムリーにトニーが帰ってきて、再会できたのである。さっそく、支援を頼んだところ「俺の彼女の父はドイツ系でVWの代理店の社長」ということで、ガラクタ部品を寄せ集めて作ってくれたのである。インフレーションが吹き荒れていたので、110ドルですんだ。トニーがいうには「中南米でクニャード(正式は義理の兄弟、通俗的には縁故・人脈等。クニャーダは姉妹)がなくなったら、社会はとまってしまうよ」というほど強力な援軍もいたのである。ラテンアメリカ文化・社会に脱帽!ものであった。
134.政府の黙認もあって、無産階級が大土地所有者の荒地に掘建て小屋を建て、所有権を主張した。やがて社会主義政府はピノチェット将軍等の軍部追われ、アジェンデ大統領は殺され、軍部が政権をとった。そして、そのピノチェット大統領政権もやがて倒れ、彼は今、被告として法廷の場に立たされようとしているが、高齢と病気で裁判にはかけられないとか。彼の部下は何人も裁判にかけられ、政権時代の犯罪をとがめられて服役している。今は再び、社会党が民主党と連立政権を組んでいる。私はアジェンデ大統領と大塩平八郎を重ねて見ていた。
135.アルゼンチン入国は問題だった。私のカルネはFIAのもので、当時、同条約を締結していないアルゼンチンやブラジルへの入国は無効だから、当初から頭痛の種だった。そこで、ここでも一計を案じた。気持ちが開放的になる土曜日の午後に、ボリビアから体当たりで入国したときは、丁度、ボクシングの世界チャンピオン大場が交通事故で亡くなり、同じ階級のボクシングでは人気があったアルゼンチンでは、役人の間で話題となっていた。係りは日本人の私に同情して、「彼は本当に強かったよなあ」等といいつつ、カルネの細部を見ないで押印したので、無事入国できたのである。奇跡だった。故大場選手の努力に感謝した。ただ、一緒のヨーロッパ人自動車旅行者は、私のカルネの無効を知っており、「黙っていてやったんだから、口止め料としてビールをご馳走しろ!」等と軽口をたたかれた。しかし、こんなことが2度あるわけはないのである。
チリから2度目の入国は、辺鄙なアンデス山中で、またも気持ちがゆるむ土曜の夕方をねらった。ところが、日頃は通過者が少なく、お暇な役人は”ひさびさの仕事”というわけで、カルネを詳細に見て、アルゼンチンの名がないことを確認してしまったのである。それから、必死の交渉が始まった。「これでは入れない」。安易に、なんとかなるだろう、と思っていたので、予想もしない役人の言葉にとまどった。あまり間をおくわけにもゆかず、考える時間がなく、とっさに「このカルネを発行してもらったときはそうだったが、今は貴国もこの条約に加入しています」「いや、無効だ」「だ---か---ら、前回ボリビアから入国したときも、OKだったんです。このページを見てください」「いや、ダメだ」。しばらく押し問答がつづき、しまいには「何なら、ブエノスアイレスの自動車クラブで確認してください」といってしまった。しかし、根拠はなかった。ただ、電話で助力をお願いすれば、何らかの道が開けるかも知れないと、一脈の望みを託したのである。
屋外にでて、5分位思案に暮れていると、「今日は休みで、連絡が確認がとれない。月曜日まで待つように」という。「そんなに待ったら、予約してあるアフリカ行きの船の乗り遅れてしまう」「----」。それから5分位、これまでの旅の内容や、今後の予定を説明して、ねばりにねばった。すると、暗くなってきた部屋で、やっと入国許可がおりた。
逃げるように一目散に国境を後にし、暗闇でどこがどうだかわからない村の空地を、一夜の宿にと駐車した。入国できたお祝いに、チリで仕入れたハマグリをガスコンロで焼き、チリワインで乾杯した。チリでエンジンは直り、悩んでいたアルゼンチンに入国できたので、これで南米最南端にゆけるし---、アフリカへの道も開ける。最高の気分で、歌も自然にでてきた。
ところが突然、車を激しくノックされた。恐る恐るサイドドアーを開けると、なんと完全武装の兵隊が4~5人、自動小銃の銃口を私に向けて立っているではないか。「お前は誰だ。何をしている。ここをどこだと思ってるんだ---」。矢継ぎ早に、質問が浴びせられた。(アルゼンチンでは、この後、何度も路上で囲まれた)とっさに、誤解は即、銃の引金の指が引かれると思い、つとめて明るく、ゆっくり事情を説明したら---、解決した。話しながら感じていたが、「言葉が上達するときは、こういうときである」、とさえ思えるほど、スラスラとスペイン語のパラブラス(単語)がでてきて、少し驚いた。
アルゼンチンの面積は、日本の約7.5倍で平野が大半である。人口は日本の約4分の1で、一人当たりの平野面積は日本の約100倍である。この広い草原=パンパのウサギは身体まで大きく、キツネ並である。この国では、誰もが安価な肉を食べられるので、貧しい私も例外ではなかった。ここではアメリカの荒野で見られるような、頂上が平らな丘=テーブルマウンテンがいくつもあり、牧童ガウチョが鉄砲をもって羊や牛を管理しており、まるで西部劇にでくわしたようである。長距離トラックの運転手もときには車を止め、鹿やウサギ等の野生動物を見かけては鉄砲を打ちまくっている。パンパでは常に風がふいており、牧場には牛と羊が草を食んでいる。南下するほど風は強くなり、寒さが増す。川には橋がなくなり、草木の背丈が短くなって牧場の柵がなくなりグアナコ(=リャーマ)、レア(アメリカダチョウ、ここではニャンドー)、野生馬、ウサギ、うずら、鹿、猪、アルマジロ、鷹等が見られる。アンデス山脈の渓流では、いたるところでニジマス釣をしたが、常に釣れた。禁漁区域では監視人と一緒にもぐりの釣をしたり---、ストローで吸って飲むマテ茶や牛肉に塩をまぶした焼肉アサード(ブラジルではシュラスコ、トルコでは一寸違うがトネルケバブ)をご馳走になったり---親切にしていただいた。日系人の集団移住地では、ブドウをつくっており、ときおり見舞われる大きな雹(ひょう)が、頭痛の種だった。
136.モレノ氷河 137.同左 138.フェリーで火の島へ139.南端は国立公園 140.パンパの砂利道
136.アルゼンチンの国立公園モレノ氷河は、3千m級のアンデス山脈の頂きから、約4km流れてアルゼンチン湖に達し、年にもよるが年に約5m動く。周囲の山には、かつて氷河が削った爪跡があちこちで見られる。
137.表面は白く、内面は青い神秘的な氷河の表面は、いたるところに亀裂が入っており、常に「ピーン!カーン!」といった音を連発し、新たな亀裂が発生していることをうかがわせている。ときどき、湖に達した氷河の、高さ70mほどの氷壁塊が湖に崩れ落ちると、大自然の静寂境に大音響が発生し、湖面に大波が立って岸辺を洗う。これらの音が、閑静な周囲の山々にこだまして、余韻を産み、まさに”自然は生きている”といった実感がわく。私はかつて、多くの自然に接してきたが、このような”自然は生きている”といった場面に出会ったことがなく、この光景にどう反応・表現してよいかわからず、腰が抜けたようにへたへたと地面に座り込んでしまった。「種の起源」の発表者ダーウィンも腰を抜かした地<である。BR>
夜は、その湖岸でキャンプした。ルアーでの夜釣りは、反応がなかった。ただ、満月が輝く静まり返った砂浜には、たくさんのウサギがでてきて、戯れ、あたかも"鳥獣戯画”を見ているような夢見心地であった。南米は、いやこの旅は苦労の連続だったが、十分に報われた、と思えるほどの感動だった。
138.アルゼンチン→チリ→フェリーで太平洋と大西洋をつなぐマゼラン海峡を渡り、チリ領のティラ・デル・フエゴ(火の島)→アルゼンチンの最南端へ。今は油田地帯で、あちこちの高い煙突からでた、油井の排ガスを燃やした炎が、寒空を焦がしていた。かつては、寒さのなかで1日中インディオが火を焚いていたのをマゼラン一行が見て「火の島」と名づけた、という説がある。その火の島は、まさしく現代の火の島になっていた。(6~9月の冬は、強風・雪・ひょう等でドライブは厳しい)
139.税金が安く、タバコやワイン等は仕入れ所のアルゼンチン南端のウシュアイア村。そこから数キロ南下すると、アメリカ大陸最南端のラパタイア国立公園だった。誰もいない。お祝いに、ウシュアイアで買ったタコを酢ダコにして、ワインで乾杯した。
なぜ、大陸の果てや岬にゆきたがるのか、は「未知のものに魅了される」「未知を知る喜び、ものごとを発見する喜びがそうさせる」「この世の果てまで見たい」「よりよい生活地はないか」等という、人類が昔から持っているものがなせる思考・行動だろう。丁度、人間がアフリカの大地溝帯でホモサピエンスになり、直立歩行になり、やがてアジア、ベーリング海峡、南北アメリカ大陸を這いまわって、ここまで辿りついた先住民の思考・行動のように。海水面が鏡のような静かな入り江でルアーを引いたが、釣れなかった。目前は太平洋と大西洋をつなぐビーグル海峡、その向島はチリのナバリノ島、その向こうは、南端の小島にケープホーン(ホーン岬)がある。
140.パンパに延々とつづく砂利道。これを横切る羊の群れ。砂利道では対向車に小石を跳ねられて、フロントガラスを割られるので、どの車も前面に金網を張っていた。この国では、VWを輸入・製造していないから、もし割られたら大変だったが、取付料の20ドルが惜しくて、取りつけずに切りぬけてしまった。車の下にも小石防止網は必要で、費用を惜しんでこれもやらず。後日は、大金を払って車の底を修理する羽目になったので、他の方には事前対応をすすめたい。節約生活はあらゆるところに及んでいたから、こんな出来事もあった。あるガソリンスタンドで、給油してもらうと、店員はよそ見をしながら入れ、満杯になってこぼれ始めても気がつかず、私の注意でやっと止めた。請求書はこぼれた分も入っていたので、「あなたの不注意でこぼれたのだから、こぼれたガソリンをタンクに入れてくれなければ断じて払わない!」、と開き直り、多少やりあった末、相手をおれさせた。
141.海洋動物の天国 142.アザラシ 143.同左 144.セイウチ 145.ペンギン村
141~145.海岸のカーボ・ドス・バイアスは動物保護区で、アザラシ約200頭、マゼランペンギン約1000頭、象アザラシ約20頭がいた。季節によっては、まったくいなくなったり、数が増えたりするという。また、季節によってはシャチ(日本名さかまた)が見られるようだ。近海および、近くのフォークランド諸島周囲は豊かな漁場で、この辺のイカは日本にも入ってくる。夢のような光景にうっとりしていると、骸と化した哀れな死体もあった。なんだか、自然の姿を垣間見たようで、人間の一生と重ねて見ると、妙な感慨に陥った。これらの風景は、北のバルデス半島まで数百キロにわたって見られ、バルデス半島では鯨も見られるという。
146.巣穴でくつろぐ 147.マル・デル・プラタ 148.同左の港 149.同左 150.ブエノスアイレス
146.マゼランペンギンか?
147.冬は人口40万人が、夏は200万人に増える保養地である。世界最大というカジノに入ると、分厚い赤いカーペットが敷かれて、独特の雰囲気をかもしだしていた。一攫千金か、わかりきった結果か?世界のカジノ公認国は113か国で、先進工業国で禁止しているのは日本のみである。
148~149.港の近くにあった日本水産㈱の支部は倒産し、職員の多くは残留して漁業を継続していた。国連決議により、沿岸の経済水域が200海里に広がる等、それらの影響がここまで及んでいたのである。花栽培、洗濯屋、養鶏業、農業、牧場経営等に従事する日系人は約300人。沖合いはよい漁場で、漁港は活気があった。ここでは魚の缶詰と塩漬けを仕入れた。
150.広大な無人のパンパから大都市に入ると、車の渋滞等で頭が痛くなる。アルゼンチンは、かつて世界第3位の自動車保有台数をもつほど、経済政策が成功したことがある。しかし、その後は低迷し、町で見かける車はほとんどが1930~1940年代で、まるでクラシックカーのオンパレードを見ているようだった。VWは見たこともないから、「何の車だ」と質問されたり、「日本は車をつくってる?本当か?」という反応には、この地が、しばらく世界の桧舞台から遠ざかっていたことをうかがわせた。
首都ブエノスアイレスでは、ヨットによる単独世界一周の途上でヨットが壊れ、修理していた青木さん(23歳)と出会った。
151.イグアス滝 152.”悪魔ののど” 153.小野さん、山中さん154.サインするペレさん155.同左
151~152.アルゼンチンからはパラグァイへ。両国の国境を流れるパラグァイでとれた魚は、みんな見たことがなく、「魚は、それぞれの環境で独自の進化をとげる」等、と思った。首都アスンシオンでは、交通信号をまったく見かけなかった。ここでは、エンジンをオーバーホールした。
パラグァイ・ブラジル・アルゼンチンの国境にあるイグアス滝は、高さ100m、滝幅5km、毎秒400トンの流量で、まさしく圧巻だった。規模もさることながら、瀑布の轟音は25km手前から聞こえるほど大きく、滝の近くでは、話し声は耳元でしないと聞こえず、雨のような飛まつですぐ濡れた。私にとっては、ここまでくることに成功した、そのご褒美の洗礼のような気がした。(後日、近くにこの水量を利用した世界最大級のイタイプー水力発電所が完成)
153.ブラジル日系人は約100万人。向かって左の小野敏松さんは、私と同じ茨城県(大津)出身で、カヌーでの零細漁業から、幾多の苦労の末にマグロ漁が成功し、サントス港に豪邸を持っていた。息子のカツトシ(勝年)さんは、サッカーの神様といわれたペレが所属するサントス・フットボールクラブのマネージャーをしていた。山中さんも同県出身で、奥さんは看護婦だが本人は失業中。にもかかわらず、子供達3人とともに飯を食わせてくれ、あつかましくもお邪魔していた---ことは感謝しつつも赤面のいたりである。なお、3人とも学業は優秀で、山中さんはそれに「あなたの気宇壮大な精神を吹きこむんだ」といって奥さんを納得させていた。
154~155.オノ・カツトシさんの紹介で、サントス・フットボールクラブのクラブハウスを訪ね、優勝時のトロフィー等を見せていただいた後で、海岸の砂浜に練習に行く前のペレにサインしてもらった。アフリカ、アジア、オーストラリアとまだまだ難関が待ち構えており、世界のスーパースターのサインは、絶大な力になると確信したからである。ペレは本名ではなく愛称だが、世界の人々にとっては、そんなことは問題外で、彼の技が傑出していたことと、人間性が共感を呼ぶのである。私の旅を支援してくれたペレさん、ムイト・オブリガード!実際、あなたのサインにはたびたび助けられましたことを、ここに謹んでご報告申し上げます。ありがとうございました。
156.コルコバードの丘 157.キリスト像 158.同左 159.サントス港 160.ヒッチで全世界を
156~158.南米からアフリカへの道(船による)は、険しかった。船便は少しあるのだが、両大陸間の交易が少ないために、船賃が高いのである。車の船賃と私の航空賃等で、手持ち資金の半分が消えるのでは、残金で広大なアフリカ大陸を、南から北へ縦横断は危険すぎた。走行距離は南米の倍以上で、道が悪いアフリカでは、必ず大きな出費が予想された。ブラジルは賃金が安くて、貯金するには長期間かかるし、またアメリカに戻って出稼ぎすれば、旅の期間はさらに伸び、その間に心変わりして、旅が頓挫しないか、車の保管はどうするか---の大問題があった。南米で会った旅人から、アルゼンチンではブエノスアイレスの船会社で、サンパウロやサントス港でもずっと情報を集めても、結果は同じだった。リオデジャネイロでは途方に暮れ、コルコバードのキリスト像に手を合わせた次第である。あの向こうにアフリカ大陸がある、だけどゆけない---。しかし「心配するな、私がついているから」と、キリスト像が私にいっている、と勝手に勇気づけたりもした。
ここで、結論に辿りつくまでは、本当に苦しかった。1人旅の限界を味わった。苦しくて、サントスの日系「三笠食堂」にゆき、主人のコブチさんと世間話をして、初めて、自分では気づかなかった単純な結論に辿りついたのである。その結論は、「安い船が見つかるまで待ち、その間にブラジルで働いて、少しでも資金を補填する」だった。
それからは、サンパウロの日本人街にある中華レストラン「タイザン=泰山」の経営者で、日系人のユサさんに雇ってもらい、コック助手として2か月間働いた。そして、まさに”待てば海路の日和あり”で、後に、念願の安い船が見つかったのである。残念ながら船は人を乗せず、船は1か月後にアフリカのアンゴラ・ルアンダ港についた。私はサンパウロ→リオデジャネイロ→南アフリカ・ヨハネスブルグ→アンゴラ・ルアンダ港に飛び、車と再び合体できた。
159.サントス港で、ギリシャ船「ウルスニス」号の甲板に車を乗せ終わったのは、午前2時半。疲労を感じない、眠くならない不思議な薬を、波止場の作業者からもらって飲んでいたので、その点はよかったが、精神的な疲れがどっと一気にでた。この日は、かつて悩み苦しみ雨に煙って沖合いが見えなかったサントス港が、快晴になった。ブラジルでは、アフリカ大陸に渡ることだけに、神経を集中せざるを得なかったので、ろくな見物もできなかった。リオのカーニバル、首都ブラジリア、アマゾン河の船旅にも興味があったが、いずれの機会にしよう。それにしても、ここブラジルでも、日系の州会議員・新聞社、その他多くの日系人のお世話になり、「日本人は世界中に相互扶助のネットワークを張っている」と、思えるほどであった。なぜ日本人は、そうなのか?他の国民で、似たような絆をもっているところはどこか。華僑は、ユダヤ人は、西欧人はどうか。それはべつにしても、改めて感謝申し上げ、みなさんのご活躍をお祈り申し上げます。
160.イグアスの滝では、日本人ヒッチハイカーの荻野洋一氏と会い、サンパウロ市まで乗せた。ところがなんと、その1年半後に、アフリカのザンビアの首都ルサカの道路で、またも”片手を上げて、親指を立てている”ではないか!この仕草は、ほぼ世界共通で、「無料で車に乗せくれ」、という意味である。彼はその後、1966年から2001.8.1現在まで、通算して11年間もヒッチハイクを主体にした旅をつづけ、2002.2.1現在で191の独立国と45の統治領等を訪れ、ヒッチハイクを主体にした旅の記録では世界一クラスになった。独立国訪問の比較は明瞭だが、統治領等の定義が統一されていないので、残念ながら、厳密な比較ができないので、世界一クラスにした。私と同様に、スタート時には十分な資金がなく、あったのは健康・情熱・親指だけで、各国でアルバイトをしながら、全世界を堪能してしまったのである。ニューヨークでは1日に3つの仕事をこなし、1年間で1万ドル以上貯めたという。写真はヨルダンとイスラエルとの間にあるアカバ湾で。
予算が少ないヒッチハイクは、あらゆる節約を強いられ、どうしても栄養失調気味になる。荷物は1グラムでも減らさないとやせた身体にこたえるので、重大な関心事である。衣類は必要最低のものを、日記帳は手帳サイズに、カメラはハーフサイズに---、と工夫が必要である。世界ヒッチハイクのノウハウは、彼の著書「面白びっくり!地球人」(KKベストセラーズ。電話03-5976-9121)を参考にするか、直接本人に問い合わせるとよい(電話0557-67-2950)。